「英語の論文読むの時間がかかる」
「苦痛」
「読んでもわからない」
「もっと楽して読めないのか」
その気持ち、めちゃめちゃわかります。
時間は有限です。
いかに楽して読むか?!
私なりのコツをまとめました。
もくじ
論文の構成を知ると読みやすくなるよ!

私の読み方 ↓
ざっくり全体→詳細
論文の構成は、同じ分野であれば一緒です。
何がどこに書いてあるかを知れば、かなり読みやすくなるよ!
- Title( タイトル)
- Authors ( 著者)
- Affiliations( 所属)
- Keywords( キーワード)
- Abstract( アブストラクト)
Main text( 本文)
- Introduction( 緒言)
- Materials and methods( 実験材料および方法)
- Results( 結果)
- Discussion( 考察)
- Conclusions ( 結論)
- Acknowledgements( 謝辞)
- References( 引用文献)
- Figures and table captions( 図表のキャプション)
論文の読み方のコツ!最初から読まない!
論文は、最初から読まないといけないと思っていませんか?
最初から読む必要はないです!
私は、以下の順で読んでいます。
”手抜きバージョン”と”じっくりバージョン”があります。
Title(タイトル)
↓
Figures & Tables(図表。最後についてるやつ)
↓
Abstract(論文の要約)
Title(タイトル)
まずはタイトルを見て、ざっと何についての論文か把握します。
Figures & Tables(図表。めっちゃ大事!)
次に、ざっと図表を眺めます。
文章よりも、図表の方が内容を理解しやすいからです。
図や表にはこの論文で言いたいことが詰まっています!
ここをチェック!!
図表のキャプション(見出しや説明)を読んでみよう。
- どういう実験をして
- どういう結果が出た
簡潔に書いてあります。
Abstract(論文の要約)
次にアブストラクトを読みます。
ここで論文の全体像をつかもう!
研究の目的と結果が簡潔に述べられています。
論文で一番大事な部分です。
”手抜きバージョン”に続き、以下を読んでいく
Conclusions(結論)
↓
Materials & Methods(方法)
↓
Results(結果)
↓
Discussion(考察)
↓
Introduction(導入。その分野の背景、主流の研究方法など)
Conclusions(結論)
著者の結論が書かれてます。短くて読みやすいです。
Results (結果)やDiscussion (議論・考察)の内容が短くまとめてられています。
ここを読んでから結果や考察に戻ると理解しやすいです。
Materials & Methods(方法)
実験や解析の方法が書かれています。
他の研究者が追認試験を行う際に必要な情報が載っています。
最初は何が書かれてるのかわからないと思いますが、同じ分野であれば、だんだん見たことがある感じになってきます。
Results(結果):FigureとTableに線を引け!
実験の結果が書いてあります。
図表の説明が出てきます。ここはとーっても大事!
チェックすべき英語は、「Fig. 1 shows ~」、「~ are shown in Table. 1」など。
図表に、この論文で言いたいことが詰まっている!
図表には必ず番号が振ってあります。
本文中の番号と照らし合わせながら読もう。
大切な箇所には線を引いておこう!
後で読み返したときにラクです。
こんなに苦労して読んだんだもの、覚えてるだろう、と思っても時間が経つとどこに書いてあったか忘れます。
日本語と違って斜め読みも時間がかかります。
読み返したとき、サッと肝心の部分を見つけられるように、チェックしておこう!!
Discussion(考察)
実験や解析の結果をもとに、著者の解釈や議論が書いてあります。
今回の結果がIntroductionで述べた問題をいかに解決したかも述べてあります。
Introduction(導入。その分野の背景、主流の研究方法など)
この研究を行うに至った背景および研究の目的が書かれています。
この分野の研究で「わかっていること」「わからないこと」「著者が述べたいこと」を斜め読みします。
読みやすいところから読もう!全くわからない論文を読むとき
私が読みやすいところは、
タイトル→図表→アブストラクト→結論
の順です。
まっっっっったくわからない論文を読むときはどうする??
そういう時は、Statistical analysisから読みます。(あれば)
私は統計解析なら馴染みがあるので、まっっっっったく知らない分野でもホッとするのです。
「おともだちに会えたー」みたいな気分になるのです。
あなたの読みやすいところはどこ?
全部読む必要はない!
論文は、全部読まないといけないと思っていませんか?
そんなことはありません!
パラグラフの最初の文章に、著者が言いたいことが書かれています。
それをチェックしよう!
まとめ
英語の論文読むの大変ですよね。
読み方なんて誰も教えてくれない…。
何もかもわからないことだらけで、英語を見ただけでめまいがするほどでした。
私は頭から全部読んでいくというやり方をしていて、すごく苦労しました。
そんなかつての私のような人へ向けて書きました。
諦めないで!
だんだん慣れてくるよ!
主婦起業コンサルタント。二児の母。「好きな時に、好きな場所で、好きなことをする!」がモットー。仕事と育児をバランス良く楽しみたい!福岡出身、千葉在住。
詳しいプロフィール→こちら☆
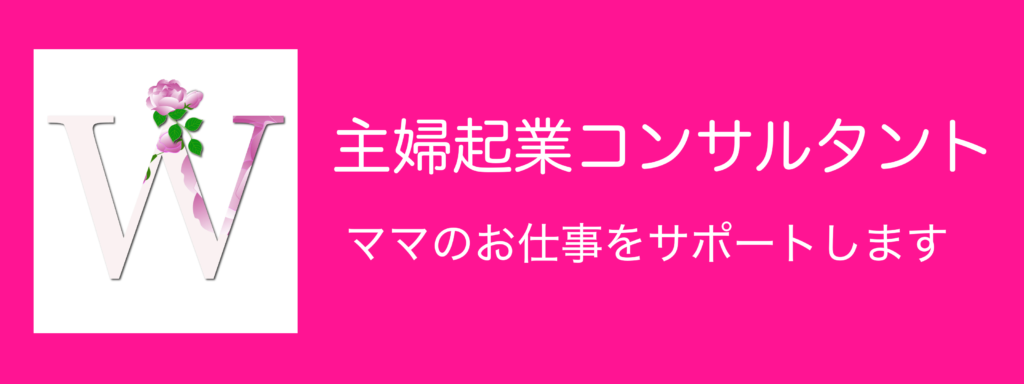



コメントを残す